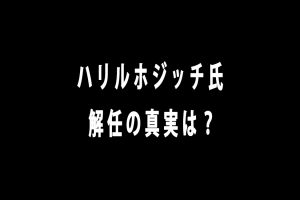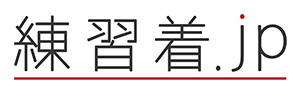日本代表は、アジアカップを準優勝で終えた。
決勝まで進んだ時の日本代表の戦績が勝率100%ということで、筆者としても心にどこか余裕を持ってしまっていたのかもしれない。
対戦相手がカタールに決まり、元日本代表監督でもあるザッケローニ氏が率いる開催国UAEとの対戦が叶わず、どこかガッカリした気持ちが先走り、カタールのことをあまり意識していなかった。
それには理由がある。
準決勝のイラン戦で、日本代表の今大会ベストマッチを観れたからだ。
これまでの不安定さがウソのように前半からチームとして機能していて、後半の得点シーンでは、先制、中押し、ダメ押しの3ゴールはゲームプランとしては理想的だった。
FIFAランク上では現在、アジア最強といっても過言ではないイランを相手に完勝した日本代表なら「決勝もいける」と多くのサポーターが思ったに違いない。
だが、今大会を冷静に振り返ると、日本はギリギリで勝ち上がってきただけで、圧勝といえる試合は全く無かった。
「よく決勝まで勝ち残った」という表現の方が正しい。
アジアカップ2019、日本代表の『準優勝』は必然だったのだ。
目次
サウジアラビア戦
1対0で勝利したが、内容では負けてもおかしくなかった。
得点シーンはセットプレーのチャンスを確実に決めていたのだから、日本代表には「勝負強さ」は間違いなくあった。
ボール支配率では、日本が23.7%に対してサウジアラビアが76.3%となっていたが、審判の笛の基準がおかしかったように感じている。
日本が攻撃に転じるときに生じた接触プレーでのファールが全て日本のファールを取っていた。
これではポゼッションが数字として上がらないのは仕方ない。
なお【中東の笛】については、また別の機会にコラムで掲載することにする。
後半途中からハーフラインから進めていないのではないか?とサッカーらしくない試合だった。
逆転の発想として、不可解なファールを取られたことでちょっとずつではあるが時間が進み、リードしている日本にとってラッキーな時間稼ぎにもなっていた。
そんな展開もあり、追加点を強引に奪いに行かず、徐々に守備重視の戦い方にシフトできたことが、勝利のポイントだろう。
日本が防戦一方でも点を取られる予感もしなかったのは、それだけサウジアラビアの攻撃陣の迫力がなく、精度の低さだけが際立っていたからだ。
※試合詳細は「日本代表:アジアカップ2019(7)サウジアラビア戦総評」にて
ベトナム戦
中盤を固めてからのカウンターを仕掛けてくるチームに日本は相対的に見て苦戦している。
ベトナムはプラスアルファで「全力プレー」があった。
もう少し足元の技術があったら日本も危なかった。
気持ちだけならベトナムだった。と見ている。
サウジアラビア戦で『サッカーらしくないサッカーを』観てしまった反動なのか、ベトナムとの試合で『サッカーらしいサッカー』を楽しませてもらった。
ただ、試合の流れを決めたのは準々決勝から導入されたVARだった。
結果として日本への判定で2度使用され、1つは歓喜から落胆。1つは落胆から歓喜につながった。
この試合の行方を左右したのは、良くも悪くもVARだった。
※試合詳細は「日本代表:アジアカップ2019(8)ベトナム戦総評」にて
イラン戦
「事実上の決勝戦」と言われた準決勝でのイラン戦。
日本が2対0とリードするまでは、相応しい試合だった。
ただ、日本が3点リードした段階でまだ時間が残っているのにも関わらず、サッカーの試合は終わってしまった。
「事実上の決勝戦」はイラン選手の愚行により汚されてしまった。
試合を通じて、グループリーグから日本代表に対して抱いていたモヤモヤは消えた一方で、なぜこの試合が最初から出来ないのか。という疑問だけ残った。
日本代表にとって今大会で初めて格上と位置付けられる国との対戦だったから。というのも大きいだろう。
また大迫選手が怪我から完全復活し、現状考えられるベストメンバーを組めたことがさらに勢いを加速させたのではないか。というのが筆者の見解だ。
1つだけ確かなことは、この試合で大迫選手が日本代表のエースストライカーになったことは間違いない。
※試合詳細は「日本代表:アジアカップ2019(9)イラン戦総評」にて
カタール戦
試合の入り方から失敗していたのだろうか。
選手にしか真意はわからないが、イラン戦とは別のチームで、ここまでなんとか耐え忍んで勝ち上がってきた日本代表に戻っていた。
前半のうちに2失点と、この時点で負け試合濃厚の展開にガッカリはした。
1点目はまだ仕方ないとしても、2点目の失点は防げたはずだったから。
2点リードはセーフティリードではないことは、日本代表にとっては十分理解しているはずだ。
ロシアW杯決勝トーナメント1回戦ベルギーとの一戦と言えば、説明不要だろう。
2点ビハインドとなった後の前半の早い時間帯で1点返す。
または後半に1点を返して、勢いのまま同点に追いつく。
このどちらかが出来ていたら試合の流れは日本側に傾いていた。
しかし、思うようなゲーム展開に持ち込めなかったのは、カタールが予想以上に組織的でチームとして完成されていたからだ。
南野選手のゴールで1点差に迫るも、カタールは慌てることなくカウンターからチャンスを伺い、PKで追加点を決めて日本の息の根を止めた。
清々しいくらいの完敗。
カタールが日本代表の倒し方をアジアで示してくれた。
筆者である私は、悔しいはずなのに少し笑っていた。
「まだまだ日本代表は強くなる」
強くなるための課題は、決勝戦でのピッチでカタールが示してくれた。
※試合詳細は「日本代表:アジアカップ2019(最終回)カタール戦総評」にて
あとがき
2019年2月1日のカタール戦は、森保体制を振り返った時に間違いなく日本にとってターニングポイントとなる試合だろう。
2018年10月、ウルグアイとの親善試合で打ち合いを制した日本代表に期待したが、失意のアジアカップから這い上がる日本代表の方が伸びしろは間違いなく大きい。
3年後の2022年カタールW杯で
「日本が躍進できたのは、2019年アジアカップの決勝でカタールに負けて準優勝に終わった悔しい経験があったから」
といったコメントが選手の口からメディアに発信されることを願う。