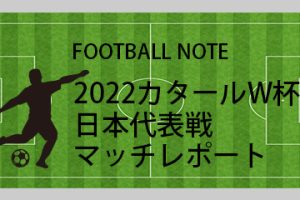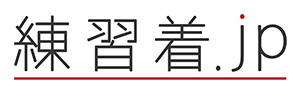決勝までたどり着いた日本代表。決勝の手はカタールに決まった。
日本はアジアカップで決勝まで進んだ時の勝率はここまで100%だったので、イラン戦のような戦い方が出来れば大丈夫だと思っていたが、勝負の世界は簡単なものではなかった。
目次
マッチレビュー
<決勝トーナメント/決勝>
日本代表 1-3 カタール代表
<スタジアム/現地情報>
スタジアム:ザイード スポーツシティ スタジアム
観客数 :36,776人
天候 :晴れ
気温 :24℃
湿度 :43%
日本代表のフォーメーション
※選手名敬称略
()内は交代出場した選手
フォーメーション:4-2-3-1
===================
大迫勇也
原口元気 南野拓実 堂安律
(武藤嘉紀) (乾貴士)
塩谷司 柴崎岳
(伊東純也)
長友佑都 吉田麻也 冨安健洋 酒井宏樹
権田修一
===================
【得点者】
後半24分;南野拓実
【編集長の考察】
前半の2失点が最後まで重くのしかかった。
前半の入りから、イラン戦とは違って試合の入りに失敗したように感じた。
先制点を奪われた場面だが、あれは相手が上手かったし、ボールが飛んだコースも仕方がない。
その後、すぐぐらいの時間帯にも危ない場面があったが吉田選手のディフェンスでなんとか持ちこたえた。
立て続けに失点していたら、前半の15分で試合が決まってしまったかもしれない。
ただ、2失点目は中盤でマークがついていなかった日本のミス。
あれだけフリーで撃たせてはダメ。
ボランチがつくのか、2列目の選手が下がってくるのか…
上手くコミュニケーション出来ていなかったかもしれない。
1点ビハインドということもあり、攻撃と守備のバランスが崩れ、全体のラインもコンパクトに保てず、間延びした時間帯に失点してしまったのは悔やまれる。
アジア、中東らしくないカタールの攻撃。
ヨーロッパの国と試合しているような印象を受けた。
後半は完全に日本のペースだった。
なぜ前半15分の入りをこのように出来なかったのか?
イランを倒して勝ち上がったことで、どこか慢心があったかもしれない。
南野選手のゴールで1点差に詰め寄って押せ押せのムードだったが、カタールのコーナーキックから、ペナルティエリア内で吉田選手がVAR判定でハンドを取られPKを与えてしまい、ダメ押しの3点目を奪われてしまい勝負あった。
『アジアカップ2019準優勝』として記録には残るが、今の日本代表を考えるとアジアでは優勝以外負けと同じだ。
カタールについて
11番のアクラム・アフィフ選手、19番のアルモンズ・アリ選手は日本にとって脅威だった。
カウンターから2人だけで、日本の守備陣をきりきり舞いにしていた。
この試合は5-3-2が基本フォーメーションだったが、対日本用の戦術だった可能性はある。
中東のチームといえど組織力が非常に高いチーム。
カタールの育成プロジェクト「アスパイア・アカデミー」の賜物だろう。
監督のフェリック・サンチェス氏はスペイン出身。
カタールの育成プロジェクト「アスパイア・アカデミー」での指導を経て、代表監督まで上り詰めた。
自国開催である2022年カタールW杯に向けて、国家を上げたチーム作りが出来ている。
日本代表:今後の課題
・大迫勇也選手のバックアップメンバー
・2列目の選手が機能しないときの対処法
・両サイドバックのバックアップメンバー
・ボランチが全体的に人材不足
・パワープレー要因
・一芸に秀でた選手
・スタメンと控え組の層の差
・戦術面での引き出しの数
・対戦相手による戦術を使い分ける柔軟性
・負けている時の交代カードの使い方
パッと思いついたことから上げてみた。
じっくり考えたらもっと出てきそうな気もするが、日本代表の課題については、今後「編集長コラム」にて隔週で掲載していきたい。
あとがき
決勝戦の審判は、決勝トーナメント1回戦サウジアラビア戦で主審を務めたラフシャン・イルマトフ氏だった。
あの時の悪い印象があったのでジャッジについては不安があったが、決勝戦は全体を通して不満はなかった。『中東の笛』はなかった。サウジアラビアとの一戦はなんだったんだろう…。
フル代表としての活動は、3月に行われる親善試合だ。
・3月22日(金)コロンビア代表
・3月26日(火)ボリビア代表
と対戦することになっている。
6月にはコパアメリカへの参加も決まっている。
現在の日本代表が南米チームと対戦してどんなサッカーができるのか?
2019年もサッカー日本代表の試合を追いかけていきます。