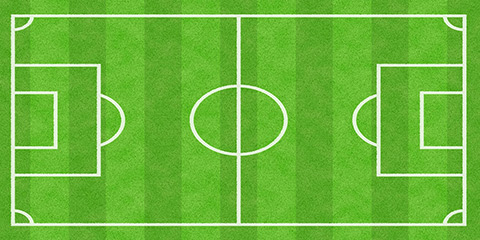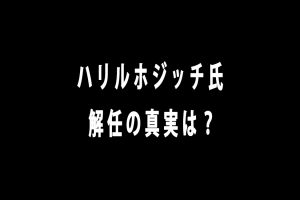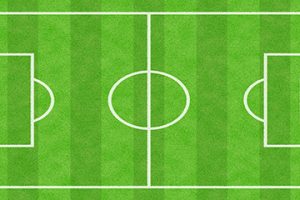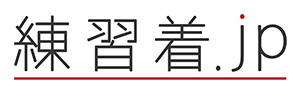先日、フランスのトゥールーズに行ってきた。
フランス リーグ・アン(第37節)/トゥールーズ対マルセイユを現地観戦するためだ。
昌子源選手と酒井宏樹選手の日本人対決にも注目だったが、2016EURO準優勝、2018ロシアW杯優勝と近年の復権に成功したフランスのフットボールをこの目で見たいと考えた。
ロシアW杯優勝メンバーの中にフランスリーグに所属する選手が少なかったといえど、フランス代表選手としてのベースを作ったのは自国リーグにあると断言できる。意外にもW杯優勝国の監督で自国監督が多いのにも、少なからず因果関係があるはずだ。
だから今回W杯優勝国の自国リーグに注目してみることにした。
日本がW杯でベスト16の壁を突破するためのカギがあると思っている。
目次
2018ロシアW杯はターニングポイント
ロシアW杯から1年を経過しようとしている。
日本代表は前評判を覆しグループリーグを突破。決勝トーナメント1回戦でベルギーに2対3で敗れ、ベスト16で敗退した。
しかし、ここに至るまでには前代未聞の監督解任劇があった。
2015年3月に日本代表監督に就任したハリルホジッチ氏。2017年8月にロシアW杯アジア最終予選を1位での突破を決めた。
だが、2018年4月に突然の解雇となった。
W杯開幕を2ヶ月後に控えた段階での監督交代は異例中の異例で、衝撃が走ったことを覚えている。残ったのは、ロシアW杯出場を決めたのはハリルホジッチ氏だが、ロシアW杯で指揮を取ったのは西野朗氏という記録だけ。
2014年ブラジルW杯のグループリーグ敗退から、ザッケローニ監督を解任し、アギーレ監督を経て、ハリルホジッチ監督で積み上げてきたものが1度リセットされ、モヤモヤだけがロシアW杯後も「外国人監督を招聘する意味は!?」というカタチで心の中にある。
確かに当時を振り返れば、采配や招集メンバー、試合後の発言など、気になる部分が多々あったのは事実だが、現時点での見解は、私たち観る側(一般メディア含む)のレベルが劣っていたのではないか。ということ。
つまり『サッカー』の枠を越えれらず『フットボール』を理解していなかったのではないだろうか。
森保一監督が就任し、新体制になり既に忘れられた過去となりつつある現在…。
1つの歴史といえばそれまでだが、今回ロシアW杯で優勝したフランスを訪れ、フランスリーグの試合を観たことで今回の考察記事の構想が出来上がった。
フランスリーグアンを観て感じたこと
トゥールーズ対マルセイユの試合を現地観戦して思ったことがある。
ハリルホジッチ氏の目指したいサッカーは、トゥールーズがこの試合で見せたプレーに近かったように感じた。
そう思った理由は「縦に速く、デュエルを制する」を体現していたサッカーをしていたからだ。特に前線の7番グラデル選手、10番レヤ・イセカ選手、14番ドセヴィ選手。この3選手は、ハリルホジッチ氏の目指すサッカーにおける攻撃のタスクを遂行しやすい構成となっている。
フランス名門のマルセイユを相手に2対2としたところまでは良かった。
シュート精度がもっとあれば、前半のうちに2対1とリードして折り返していた可能性もある。
マルセイユのグスタボ選手のところでボールを奪ってからのショートカウンターは、非常に効果的だった。
高い位置でボールを奪ってからのショートカウンターは、ハリルホジッチ氏がアジア最終予選のオーストラリア戦で見せた戦術の1つでもある。
トゥールーズというチームが、1部リーグの中堅クラブになるためには、中盤のアンカーポジションにチームを統率できるタイプの選手が入ればもっと安定した成績が残せるだろう。
マルセイユ戦の後半、2対3と1点リードを許してしまい、そこから点を取るために攻撃的に行ったことで、サイドのウラのスペースをつかれ、カウンターから立て続けに失点してしまった。守備的MF(ボランチ)とサイドバックの守備力には物足りなさを感じていた。
もしハリルホジッチ氏がトゥールーズの監督に就任した場合、補強の乗り出すなら日本人選手でいえば、長谷部誠選手(フランクフルト)がリストには上がるだろう。当時、ハリルジャパンでも代えの効かない選手であることを名指しで明言していたほどだったから。
ハリルホジッチ氏はフランスリーグの中堅クラブで1番輝くと思うのは、リーグ全体が「縦に速く、デュエルを制する」サッカーを体現していること。
フランスリーグの強豪クラブには技術の高い選手が揃っているので「シャンパンサッカー」を体現することも可能だから、あえてステップアップを目指すハングリー精神を持った選手の多い中堅クラブを例に挙げさせてもらった。
ナントの監督に今季(2018-2019シーズン)途中から就任し、1部リーグを12位で終えたことも1つの根拠だ。
ハリルホジッチ氏が就任する前、ナントは第8節を終えて「1勝4敗3分」と低迷していた。第9節ボルドー戦からの指揮となってから「12勝12敗6分」とほぼ5割の勝率で、1部残留を果たした。
クラブと代表の違いはあるが、監督としての手腕には疑いの余地はないのだ。
世界レベルまで辿り着けなかった日本代表
ハリルホジッチ氏がロシアW杯前に解任された事実は変わらない。
日本代表を世界レベルに押し上げる道半ばでハリルジャパンは解体となった。
目指していたのは、縦に速く、球際で負けないサッカーであり、実にシンプルなものだ。そして最大の武器は、相手チームの急所を突くいやらしいサッカーだと思う。
所属クラブでコンスタントに出場し、怪我などのコンディション不良が無かった場合、あくまで想像の域ではあるが、予想スタメンを考えてみた。
【予想フォーメーション:4-3-3】
===================
大迫勇也
(本田圭佑/岡崎慎司)
原口元気 清武弘嗣
(乾貴士) (浅野拓磨/久保裕也)
井手口陽介 山口蛍
(香川真司/柴崎岳) (大島僚太/遠藤航)
長谷部誠
長友佑都 昌子源 吉田麻也 酒井宏樹
(槙野智章)
川島永嗣
<攻撃の切り札>
・宇佐美貴史
・中島翔哉
===================
ベースはあくまで、アジア最終予選オーストラリア戦のメンバーで、ロシアW杯出場権獲得後の親善試合で試したメンバーも考慮してみた。
ハリルホジッチ氏にとっての誤算は、清武弘嗣選手を招集できなかったことだろう。
ハリルジャパンでは、本田選手、香川選手に代わって中盤の攻撃のキーマンとなっていただけに、当時所属していたセビージャで出場機会を無くし、怪我も重なったことでコンディションを崩し代表から遠ざかってしまった。
井手口陽介選手も誤算となった1人だ。
井手口選手はアジア3次予選のイラク戦で代表初先発とハリルホジッチ氏から抜擢された。2018年1月海外移籍したが、出場機会を失ってしまい代表からも遠ざかった。
総合的に判断して、前線から運動量を活かして守備が出来るメンバーとなった。
中盤でパスを繋いでペースを作るのではなく、ドリブルから前への推進力で攻撃に移る。攻守の切り替えが早く、球際が激しく行ける選手を重宝する。攻撃の切り札として中島翔哉選手はメンバー入りしていただろう。と予想した。
対戦相手によって少なからずメンバーの入れ替えはあるが、基本フォーメーションは「4-3-3」か「4-2-3-1」になるだろう。試合中にシステムは細かく変更されるが、4バックだけは既定路線だったように思う。少なくてもこの時点で3バックは考えられなかった。
最終ラインはバックアップを含めて、ほぼ決まっていたとみている。
ディフェンス陣はW杯本大会でもある程度戦える自信はあったはずだ。
ただ、中盤の構成について頭を悩ませていたのは、親善試合でのメンバー招集を見てもわかる。右のサイドアタッカーの人選も同じだ。
ロシアW杯まで半年を切った頃、出場機会を失った選手、怪我やコンディション不良でプレーできなかった選手が中盤の選手に特に多かった。
ハリルホジッチ氏の失敗は、前線、中盤の選手を世界レベルまでに持っていけなかったこと。
人材は多いが、デュエルに強い選手が見当たらなかったのだろう。
仮にメンバーを固定したとしてもW杯開幕までに、個のレベルを上げる時間が足りなかった可能性もある。
コロンビア、セネガル、ポーランドを相手にしたときに、総合的に判断して戦える選手が、ロシアW杯メンバーに選出されていただろう。たとえサポーター、メディアから大バッシングを受けたとしても…。
2018-2019シーズンの海外組の所属クラブでの成績を見た時、ヨーロッパでコンスタントに出場機会を得ていたのは、ハリルホジッチ氏から評価が良かった選手だというのは、ただの偶然ではない。
成績不振による監督解任問題
監督解任問題についても考えたい。
今回は「フランス リーグアン」の試合を現地観戦したことで構想が出来たので、フランスリーグの監督事情についても掘り下げることにする。
トゥールーズのアラン・カサノヴァ監督[フランス]は1部残留という至上命題を達成したので続投が決定的となっている。
マルセイユのリュディ・ガルシア監督[フランス籍]は、リーグ5位に終わり、来期ヨーロッパリーグ(EL)の出場権を逃したことも影響したのか退任の意向を示していて、先日アンドレ・ビラス・ボアス新監督[ポルトガル籍]の就任を発表した。
今季フランス リーグアンでシーズン中に解任となったのは、ナントのミゲル・カルドーゾ監督[ポルトガル籍] 開幕から1勝4敗3分と第8節を終えて降格圏の19位と下位に低迷していたため解任。後任にハリルホジッチ氏[フランス籍]が就任し、チームを立て直し1部残留を果たした。
モナコのレオナルド・ジャルディム監督[ポルトガル籍]も、シーズン中の解任となったが意外な展開が待っていた。
開幕から1勝5敗3分と、昨シーズンリーグ2位のクラブが不振に陥り10月に解任。後任にティエリ・アンリ監督[フランス籍]が就任したが、指揮を執った12試合で2勝7敗3分と立て直しに失敗してしまう。
21試合を終え、3勝12敗6分と降格圏に沈んていたため、アンリ監督を解任。
前監督のジャルディム氏が解任からわずか3か月で復帰することになる珍しい事態になったが、モナコは今季17位となり1部リーグ残留を決めている。
各クラブチームの事情は異なるが、1部リーグ残留のための「監督交代」はこの世界では当たり前。というのは大前提である。
Jリーグでも同じ現象は起こっている。
今シーズンでは、清水エスパルスのヤン・ヨンソン監督が成績不振により解任。
先日浦和レッズのオズワルド・オリベイラ監督も解任された。
オリベイラ監督は、鹿島アントラーズ時代の実績、今シーズンのACLではグループリーグ突破と最初の関門は突破したにも関わらず、リーグ戦の低迷が原因で解任となった。
一方、日本人監督の電撃解任は少ない印象を受ける。
シーズン終了をもって契約満了がほとんどのような感じがしているのは気のせいだろうか。
2019年5月31日現在、15位ジュビロ磐田の名波浩監督、16位ガンバ大阪の宮本恒靖監督は、両クラブのこれまでの功績を考えると、いつ解任されてもおかしくない状況だ。
ただ、両監督とも選手時代は代表クラスの選手であり、所属チームの顔ともいえる存在だった。
そういった理由で解任に踏みとどまっているなら、球団がプロフェッショナルな決断としているとは言い難い。
成績不振の責任を取って、現場のトップである監督が辞任するのは仕方ない。
ただ、監督が辞めることは、選手にも責任があるということをメディアが伝えていかないと、監督に責任を押し付けた形だけになってしまう。クラブでも代表でもそれは変わらない。
2014年ブラジルW杯グループリーグ敗退後のザッケローニ監督辞任の時もそうだった。期待を裏切る結果に、各メディアが一斉に手のひらを返してバッシングを行った。
バッシングについては、この世界では当たり前のことなので、敗者は受け入れるしかない。勝負の世界に生きる者にとって宿命だからだ。
ただ、そこに至るまで長い時間をかけて築き上げてきたものまで、監督の責任にして一斉に攻め立てるのはどうだったのか。私はこの時のメディア報道に嫌気がさして、一時期サッカーに関する記事を読むのを辞めた記憶がある。
在任中に掴んだ栄光、実績、積み上げて来たものを、解任後に無かったことのように批判することに意味はない。2018年4月のハリルホジッチ監督電撃解任を越える悲劇が生まれないことを望んでいる。
あとがき
トゥールーズFCは、フランス1部リーグで1部残留を目標にしているチームである。とある記事では「野心のないクラブ」と揶揄されていた。
実際に現場を見て感じたのは、野心がないのは集客やイベントの部分であり、サッカーの内容自体はヨーロッパのスタンダードだった。練習を見る限り選手の中には野心に溢れた選手もいた。そうでなければ各国代表選手が集まる名門マルセイユを相手に、後半途中までとはいえ接戦を演じることはできない。
2019年1月に日本代表DFの昌子源選手が移籍しなければ、トゥールーズFCというクラブにそこまで注目していたかわからない。
ただ、パリサンジェルマン、マルセイユ、リヨンといった名門クラブの試合だけではなく、中堅クラブの試合を観ることで、今回の考察記事が生まれたのは私にとっても新たな発見だった。
日本代表がハリルホジッチ監督としてW杯本大会に挑んでも、グループリーグで敗退しパッシングを受けたかもしれない。ベスト16敗退だったとしても、前評判以上の成績を出したことで手のひらを返した評価を受けたかもしれないし、初のベスト8進出に日本中が歓喜したかはわからない。
2019年4月10日、ハリルホジッチ氏側が訴訟を取り下げることで電撃解任騒動の幕引きが行われた。
しかし、コミュニケーション不足が理由での監督解任は、私たちの知らないところで火種として残っていて、別の問題が出てきた時に、再度燃え上がる気がしてならない。
日本がW杯でベスト16の壁を越えるためには、チームの成績不振を監督問題として処理せず、選手の個の力をどこまで世界レベルに引き上げれるのか?にフォーカスする必要がある。